「簿記2級と取得したいけど、どれくらい難しいの?」
「独学でも合格することはできるの?」
「簿記2級を取得するための効果的な勉強方法はあるの?」
簿記2級の取得を目指す際、「難易度が高い」と聞いて、挑戦をためらっている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、簿記2級の試験内容や合格率、独学で簿記2級に合格するためのポイントなどを分かりやすく解説します。
これから簿記2級の取得を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
簿記2級とは?
日商簿記2級は、単なる帳簿付けの技術を超え、企業の財務諸表を読み解き、経営状況を分析する能力を証明する、実用性の高い資格です。
日本商工会議所が「経営管理に役立つ知識として、企業から最も求められる資格の一つ」と位置付けている通り、その価値は社会的に広く認知されています。
具体的には、高度な商業簿記に加え、製造業のコスト管理に不可欠な工業簿記(原価計算)の知識が問われます。
これにより、取得者は多様な業種で即戦力となりうる会計スキルを持つと見なされ、経理専門職はもちろん、キャリアアップを目指すすべてのビジネスパーソンにとって強力な武器となるのです。
簿記3級との違い
簿記2級と3級の決定的な違いは、試験範囲に「工業簿記」が加わること、そして「商業簿記」の内容が大幅に高度化・複雑化する点にあります。
この変更により、学習すべき範囲は量・質ともに飛躍的に増大し、求められる知識レベルも全く異なるものになります。
簿記3級が個人商店などの基本的な商業簿記を扱うのに対し、2級では株式会社の複雑な会計処理や、製造業における原価計算を扱う工業簿記が新たに出題されます。
このため、転職市場においてもその評価は大きく異なり、多くの企業が経理職の応募資格として「簿記2級以上」を明記しているのが現状です。
3級が基礎知識の証明であるのに対し、2級は実務能力の証明として社会的に評価されています。
簿記2級の難易度
簿記2級の難易度は、合格率だけを見ると非常に高い水準にありますが、その実態は一様ではありません。
この試験は、点数が70点以上であれば合格となる「絶対評価」を採用しており、試験問題自体の難易度が直接合格率に影響します。
特に、従来のペーパー形式で行われる統一試験では、回によって合格率が10%台にまで落ち込むこともあり、「難しい」という印象を強くしています。
一方で、近年導入されたネット試験(CBT方式)では、合格率が比較的安定している傾向が見られます。
したがって、簿記2級の難易度を正しく評価するには、自分がどちらの試験形式で挑戦するのかを考慮に入れることが重要です。
簿記2級の合格率
簿記2級の合格率は、試験形式によって顕著な差があり、統一試験(ペーパー試験)が平均20%前後であるのに対し、ネット試験(CBT方式)は約35%〜40%と高い水準で推移しています。
この合格率の差は、簿記2級の難易度を考える上で見逃せないポイントです。
例えば、第165回(2023年11月)の統一試験の合格率が11.9%と極めて低かったのに対し、2023年度のネット試験は35.2%と安定していました。
日本商工会議所は両試験の難易度に差はないとしていますが、ネット試験は随時受験可能で学習が完了したベストなタイミングで挑戦できるため、受験者にとって実力を発揮しやすい環境が整っていると考えられます。
この事実から、戦略的にネット試験を選択することが、合格への近道となり得ることがわかります。
簿記2級が難しい理由3選
簿記2級が多くの受験者にとって「高い壁」と感じられるのには、いくつかの明確な理由があります。
これらの要因を事前に理解し、それぞれに的を絞った対策を講じることが、合格への道を切り拓く鍵となります。
ここでは、簿記2級の難易度を押し上げている主要な3つの理由を深掘りし、その本質に迫ります。
1.出題範囲が広いため
簿記2級が難しいと感じられる最大の理由は、その圧倒的に広い出題範囲にあります。
簿記3級の知識を前提としながらも、学習すべき論点は量・質ともに格段に増加し、実務で求められる高度な会計知識が網羅されています。
特に近年では、これまで簿記1級の範囲であった「連結会計」や「税効果会計」、「リース会計」といった専門的な論点が2級の試験範囲に加わりました。
これらの内容は、企業の複雑な経済活動を正確に財務諸表に反映させるためのものであり、理解するには相応の学習時間と努力が必要です。
この広範な試験範囲こそが、簿記2級の高い専門性と価値を担保しているのです。
2.工業簿記が出題される
簿記2級の難易度を大きく引き上げているもう一つの要因は、新たに登場する「工業簿記」です。
工業簿記は、商業簿記とは根本的に異なる思考法が求められるため、多くの初学者がつまずくポイントとなっています。
商業簿記が外部との取引(仕入・販売)を記録するのに対し、工業簿記は企業内部での「モノづくりのコスト」を計算する原価計算が中心です。
材料費や人件費、経費が製品の原価にどのように集計されていくのかというプロセスを理解する必要があり、特に製造業に馴染みのない人にとってはイメージしにくく、難解に感じられます。
この新しい概念への対応が、簿記2級合格の大きなハードルの一つと言えるでしょう。
3.本試験問題が公開されていない
簿記2級の学習を難しくしている要因として、本試験の問題が公式に公開されていないという事実があります。
著作権の問題や、ネット試験における問題の多様性を維持するため、受験者は過去の試験問題を直接入手して対策することができません。
これにより、大学受験のように「赤本」を解いて出題傾向を掴むといった王道の学習法が使えず、市販の予想問題集や資格予備校が提供する教材に頼ることになります。
ネット試験(CBT方式)では受験者ごとに異なる問題が出題されるため、問題の非公開は必然的な措置とも言えます。
この状況は、信頼できる教材を自ら見極めて選ぶことの重要性を高めており、独学者にとっては情報収集能力も試される一因となっています。
日商簿記2級試験の概要
商簿記2級は、日本商工会議所が主催する、企業の高度な会計実務能力を測るための検定試験です。
試験は「商業簿記」と「工業簿記」の2科目で構成され、試験時間は90分、100点満点中70点以上の得点で合格となります。
受験資格に学歴や年齢などの制限はなく、誰でも挑戦することが可能です。
大きな特徴として、年3回特定の日に行われる「統一試験(ペーパー試験)」と、テストセンターで随時受験できる「ネット試験(CBT方式)」の2つの受験方法が用意されています。
どちらで合格しても資格の価値は全く同じであり、自分の学習スタイルやスケジュールに合わせて最適な形式を選択できます。
商業簿記
商業簿記は、簿記2級試験の配点の60%を占める中心的な科目であり、株式会社の実践的な会計処理能力が問われます。
簿記3級で学んだ基礎的な知識を土台としながらも、その内容は格段に専門的かつ複雑になります。
具体的には、複数の企業グループ全体の財政状態を示す「連結会計」や、法人税の計算を会計上の利益と調整する「税効果会計」、設備の賃借に関する「リース会計」といった、大企業の経理実務に不可欠な高度な論点が主な学習範囲です。
これらの知識を習得することで、企業の財務諸表をより深く、正確に読み解く力が養われ、経営分析のスキルが身につきます。
工業簿記
工業簿記は、簿記2級試験の配点の40%を占める科目で、主に製造業における「原価計算」の知識が問われます。
この科目は、製品を一つ作るためにどれだけのコストがかかったかを正確に把握し、管理するためのスキルを測るものです。
外部との取引を記録する商業簿記とは異なり、工業簿記は企業内部での材料費、労務費、経費といったコストが、製品の完成に至るまでにどのように集計・分類されていくかという「原価の流れ」を追跡します。
この原価計算の知識は、製品の価格設定や利益計画、コスト削減といった経営判断の根幹をなすため、非常に実践的です。
初学者には難しく感じられる分野ですが、一度パターンを理解すれば安定した得点源となるため、合格には攻略が不可欠です。
簿記2級の出題形式について
簿記2級の受験を成功させるためには、2種類ある出題形式、「統一試験」と「ネット試験(CBT方式)」の違いを理解し、自分に合った方を選ぶことが重要です。
両者は試験日や会場、合否の確認方法などが異なり、それぞれにメリットとデメリットが存在します。
合格した場合の資格の価値に優劣はありませんので、ご自身の学習の進捗状況や生活スタイル、さらには性格などを考慮して、最適な受験方法を戦略的に選択しましょう。
以下で、それぞれの試験形式の特徴を詳しく解説します。
統一試験
統一試験とは、年に3回(6月、11月、2月)の指定された日曜日に、全国の商工会議所が用意した会場で一斉に行われる伝統的なペーパー形式の試験です。
この試験のメリットは、試験日が固定されているため学習計画を立てやすい点や、問題用紙や解答用紙に直接書き込みながら思考を整理できる点にあります。
計算過程のメモや重要な箇所へのマーキングなど、紙媒体ならではの学習スタイルを本番でも活かしたい方に向いています。
一方で、受験機会が年に3回と限られているため、不合格だった場合は次のチャンスまで数ヶ月待つ必要があります。<また、合否発表までに2〜3週間を要するため、すぐに結果を知りたい方にとってはもどかしく感じられるかもしれません。
ネット試験(CBT方式)
ネット試験(CBT方式)は、全国各地に設置されたテストセンターのパソコンを使い、自分の都合に合わせて随時受験できる柔軟性の高い試験形式です。
この方式の最大の利点は、試験休止期間を除き、会場の空きさえあればいつでも受験を申し込める点にあります。
これにより、学習の進捗が最高潮に達したタイミングで試験に臨むことができ、合格の可能性を最大限に高めることが可能です。
さらに、試験終了後すぐにその場で合否が判明するため、結果を待つストレスがなく、すぐに次の行動(再挑戦の計画や就職活動など)に移れます。
ただし、問題用紙への書き込みはできず、配布される計算用紙と画面を見ながら解答を進めるスタイルに慣れるための練習が必要です。
簿記の試験内容、スケジュールを詳しく知りたい方は下記をご覧ください
参照:商工会議所の検定試験
簿記2級に合格するために必要な勉強時間の目安
簿記2級の合格までに要する勉強時間は、受験者が簿記3級レベルの知識を持っているか否かによって大きく変動します。
自分の現在地を正確に把握し、それに基づいた現実的な学習計画を立てることが、挫折を防ぎ、着実にゴールへ向かうための第一歩です。
ここでは、それぞれのケースで一般的とされる勉強時間の目安を示しますので、ご自身の状況と照らし合わせ、無理のない学習スケジュールを設計するための参考にしてください。
簿記3級に合格している場合
すでに簿記3級の知識を習得している方が2級合格を目指す場合、一般的に150時間から350時間程度の勉強時間が必要とされています。
この時間の幅は、3級の内容をどれだけ深く理解し、定着させているかによって変わります。
3級の知識が盤石であれば、2級で新たに追加される論点の学習にスムーズに移行できるため、比較的短期間での合格が可能です。
例えば、独学で250時間を目標とする場合、1日2時間の学習を確保できれば約4ヶ月で達成できる計算になります。
重要なのは、単に「3級に合格した」という事実だけでなく、その知識を自在に使いこなせるレベルにあるかどうかです。
簿記を勉強するのが初めての人
簿記の学習経験が全くない初学者が簿記2級の合格を目指す場合、250時間から500時間という、より長期間の勉強が必要になります。
この時間には、まず簿記の基礎である3級レベルの知識を習得するための学習時間(約100時間)が含まれています。
市販されている簿記2級の教材のほとんどは、3級の知識があることを前提に作られているため、基礎を飛ばして学習を進めることは非効率的かつ困難です。
1日2時間の学習時間を確保した場合、350時間なら約6ヶ月、500時間なら8ヶ月以上を要する計算となります。
したがって、初学者の方はまず3級の内容を確実にマスターすることを第一目標とし、段階的にステップアップしていく学習計画を立てることが、最終的な合格への最も確実なルートと言えるでしょう。
独学で簿記2級を合格するための5つのポイント
簿記2級は決して簡単な試験ではありませんが、正しい戦略と効率的な学習法を実践すれば、独学でも十分に合格を狙うことができます。
特に、自分のペースで学習を進めたい方にとって、独学は有効な選択肢です。
しかし、闇雲に勉強を始めても広大な試験範囲に圧倒されてしまいがちです。
ここでは、独学での合格を確実なものにするための、5つの重要なポイントを具体的に解説します。
これらの要点を押さえることで、あなたの努力を最大限に成果へと結びつけましょう。
1.自分に適したテキストや参考書を選ぶ
独学における成否を分ける最初のステップは、自分に最適なテキストや参考書を選ぶことです。
本試験問題が非公開である以上、市販の教材が学習の質を決定づける最も重要なツールとなります。
まず絶対条件として、試験範囲の改定に対応した「最新版」のテキストを選びましょう。<br><br>参考:最新のテキストを選ぼう!
その上で、書店で実際に手に取り、図解の多さや解説の口調など、自分が「理解しやすい」「続けやすい」と感じるものを選ぶことが肝心です。
例えば、イラストが豊富で初学者にも分かりやすいと評判の「みんなが欲しかった!簿記の教科書」シリーズや、実践的な下書きの書き方に定評のある「パブロフ流」シリーズなど、それぞれに特徴があります。
また、学習効率を最大化するために、テキストと問題集は同じシリーズで統一することをおすすめします。
2.問題集や公開されているサンプル問題を繰り返し解く
簿記の知識を本当に自分のものにするためには、テキストを読むインプット学習だけでなく、実際に問題を解くアウトプット学習が極めて重要です。
テキストを一通り読んで全体像を掴んだら、できるだけ早く問題演習に移り、解答能力を徹底的に鍛えましょう。
重要なのは、間違えた問題の解説を熟読し、「なぜ間違えたのか」を根本から理解することです。
そして、自力で正解を導き出せるようになるまで、何度も繰り返し解き直すことで、知識は確実に定着し、解答スピードも向上します。
また、日本商工会議所の公式サイトで公開されているサンプル問題は、本試験のレベルや形式を体感できる貴重な教材ですので、必ず一度は解いておきましょう。
3.ベースとなる簿記3級の復習もする
簿記2級の学習を成功させるためには、その土台となる簿記3級の内容を完璧に理解していることが大前提となります。
簿記2級のカリキュラムは、3級で学ぶ仕訳や勘定科目、決算手続きといった基礎知識が完全に身についていることを前提に組まれています。
この基礎が揺らいでいる状態で応用的な学習に進んでも、理解が追いつかず、挫折の原因になりかねません。
本格的に2級の学習を始める前に、3級のテキストを再読したり、問題集を解き直したりして、基礎知識に漏れがないかを確認しましょう。
この一見遠回りに思える復習こそが、結果的に2級の学習効率を高め、合格への最短ルートを築くのです。
4.間違えやすい問題や苦手分野はマスターしておく
独学で合格を掴むためには、自分の弱点と向き合い、それを徹底的に克服する学習姿勢が不可欠です。
広大な試験範囲の中では、誰しも「理解しにくい論点」や「何度も間違えてしまう問題」に遭遇します。
これらを放置せず、早期に特定し、集中的に対策することが合否を分けます。
具体的な方法として、間違えた問題を記録する「ミスノート」の作成が非常に有効です。
問題の内容、間違えた原因、正しい解法を書き出すことで、自分のミスの傾向を客観的に分析し、同じ過ちを繰り返すのを防ぎます。
特に多くの受験生が苦戦する連結会計や工業簿記などは、テキストの該当箇所を読み返し、類題を繰り返し解くことで、苦手意識を克服し、得点源に変えていきましょう。
5.工業簿記から学習を進める
学者が簿記2級を効率的に攻略するための有効な戦略として、「工業簿記から学習を始める」という方法があります。
一般的には商業簿記から手をつけることが多いですが、この順番を逆転させることで、学習のモチベーション維持と効率化が期待できます。
その理由は、工業簿記が商業簿記とは独立した分野であり、出題範囲が比較的コンパクトにまとまっている上に、問題の出題パターンがある程度定まっているためです。
最初に工業簿記をマスターし、配点の40%を占めるこの科目を安定した得点源にできれば、精神的な余裕が生まれます。
この自信を土台に、より範囲が広く複雑な商業簿記の学習にじっくりと取り組むことができるのです。
この戦略は、学習のペースメーカーを自分で作らなければならない独学者にとって、特に効果的なアプローチと言えるでしょう。
簿記2級を受ける際の注意点3選
簿記2級の合格を確実にするためには、会計知識を身につけるだけでなく、試験本番で実力を最大限に発揮するための「受験テクニック」を習得することが不可欠です。
特に、90分という限られた時間内で、膨大な量の問題を正確かつ迅速に処理する能力が試されます。
ここでは、合否に直結するにもかかわらず見落とされがちな、本番での3つの重要な注意点を解説します。
これらのポイントを日頃の学習から意識することで、本番でのパフォーマンスを大きく向上させましょう。
1.試験時間内での時間配分を考えておく
簿記2級の試験は時間との勝負であり、90分という限られた時間内で合格点の70点を確保するためには、事前に時間配分を計画しておくことが極めて重要です。
多くの合格者が実践している有効な戦略は、得点しやすく、解答パターンがある程度決まっている問題から優先的に解くことです。
具体的には、「第1問(仕訳)→第4問・第5問(工業簿記)→第3問(決算)→第2問(個別論点)」という順番が推奨されています
例えば、第1問に15分、工業簿記(第4・5問)に30分、第3問に30分、第2問に10分、見直し5分といった具体的な時間配分を決め、普段の演習からこの時間感覚を身体に染み込ませておくことが、本番での成功の鍵となります。
2.電卓操作に慣れておく
記試験において電卓は、単なる計算機ではなく、時間短縮と正確性向上を実現するための重要な武器です。
特に、複数の計算結果を一時的に保存・集計できる「メモリーキー(M+,M-)」や、計算結果の合計を瞬時に出す「グランドトータルキー(GT)」の活用は必須です。
例えば、複数の掛け算の結果を合計する場合、GTキーを使えば、各計算結果をメモする必要がなく、一度の操作で総計を求めることができます。
また、右利きの人は左手で電卓を操作する練習を積むことで、右手で解答を記入しながら同時に計算を進められ、大幅な時間短縮につながります。
日頃から同じ電卓を使い込み、キーの位置を見ずに打てるレベルまで習熟しておくことが、本番での余裕を生み出します。
3.分からない問題は後回し、分かる問題から解き始める
合格ラインである70点を確実に確保するためには、「分からない問題に固執せず、勇気を持って後回しにする」という戦略的な判断が不可欠です。
簿記2級の試験では、時に非常に難解な問題や、対策が手薄な論点が出題されることがあります。
そうした問題に時間を費やしすぎると、本来確実に得点できるはずの他の問題に取り組む時間がなくなり、結果として不合格になってしまいます。
試験が始まったら、まず全問題に目を通し、自分が得意とする分野や、確実に解けると判断した問題から手をつけるのが賢明です。
満点を取る必要はなく、「取れる問題を確実に取る」という意識を徹底することが最も重要です。
難しい問題は、全て解ける問題を終えた後に、残った時間で挑戦するという冷静な姿勢で臨むことが、合格の可能性を最大化します。
簿記2級の資格が活かせる仕事・転職に有利な仕事
簿記2級は、その高い専門性と実用性から、経理・会計分野にとどまらず、非常に幅広い職種で高く評価される資格です。
この資格が証明するのは、単なる記帳スキルではなく、「企業の財務状況を数字に基づいて客観的に分析・理解できる能力」です。
この能力は、あらゆるビジネスの根幹をなすものであり、多くの企業が採用やキャリアアップの際に重視します。
ここでは、簿記2級の資格が具体的にどのような仕事で活かされ、転職市場で有利に働くのか、代表的な5つの職種を例に挙げて解説します。
1.一般企業の経理部門
簿記2級の知識が最も直接的に活かせるのは、あらゆる企業の根幹を支える経理・財務部門です。
多くの企業が経理職の募集要件として「日商簿記2級以上」を掲げており、この資格は経理キャリアのスタートラインとも言えます。
日々の仕訳や伝票処理といった基本的な業務から、月次・年次決算の作成、財務諸表の分析といった、より高度で責任のある業務まで任されるようになります。
たとえ実務経験がなくても、簿記2級を保有していることで会計に関する体系的な知識と学習意欲を証明でき、未経験から経理職への転職を目指す際にも大きな強みとなります。
2.経営企画部門
企業の羅針盤とも言える経営企画部門においても、簿記2級のスキルは極めて高く評価されます。
経営企画の主な役割は、自社や競合の経営状況を分析し、予算編成や新規事業の立案、中長期的な経営戦略を策定することです。
これらの業務を遂行する上で、財務諸表を正確に読み解き、企業の財政状態や収益性を客観的に把握する能力は必須です。
例えば、新たな設備投資の採算性を評価したり、M&A候補企業の価値を算定したりする場面で、簿記2級で学んだ原価計算や連結会計の知識が直接的に活かされます。
数字に基づいた説得力のある戦略を立案できる人材は、経営層からの信頼も厚く、キャリアの可能性を大きく広げることができます。
3.会計事務所
会計事務所は、簿記2級の知識を活かし、会計のプロフェッショナルとしてキャリアを積むための絶好の環境です。
主な業務は、クライアントである中小企業の記帳代行や給与計算、決算書の作成支援など、経理業務全般にわたります。
簿記2級レベルの高度な商業簿記・工業簿記の知識があれば、即戦力として多様な業務を担当することが可能です。
様々な業種のクライアントを担当することで、短期間で幅広い経理実務を経験できるのが大きな魅力です。
この経験は、将来的に一般企業の経理部門へ転職する際にも高く評価されます。
また、公認会計士や税理士といった専門家と働くことで、自身のスキルアップにも繋がり、上位資格への挑戦の足がかりにもなります。
4.税理士事務所
税理士事務所は、簿記2級の知識を基盤に、より専門性の高い税務会計の分野で活躍できる職場です。
税理士の補助として、クライアント企業の会計帳簿の作成や決算業務を担当し、税務申告の基礎となる正確なデータを作成することが主な役割となります。
クライアントから預かった証憑類を元に仕訳を行い、月次試算表を作成するといった一連の業務は、まさに簿記2級で培った知識とスキルが直接活かされる場面です。
多くの税理士事務所は会計事務所としての機能も併せ持っているため、記帳代行から決算サポートまで、幅広い実務経験を積むことができます。
将来的に税理士を目指す人にとっては、実務経験を積みながら試験勉強を進められる、理想的なキャリアパスと言えるでしょう。
5.コンサルティング会社
経営コンサルティング会社、特に財務アドバイザリーサービスを提供するファームでは、簿記2級の知識は必須スキルと見なされます。
コンサルタントの仕事は、クライアント企業の経営課題を解決に導くことですが、その第一歩は財務諸表の分析から始まります。
簿記2級の知識があれば、貸借対照表や損益計算書といった財務データを深く読み解き、収益性の問題点やコスト構造の課題などを的確に抽出できます。
例えば、クライアントの財務状況を分析して資金繰り改善策を提案したり、事業再生計画を策定したりする際に、簿記2級で学んだ知識がその土台となります。
会計というビジネスの共通言語を使いこなし、数字に基づいた論理的な提案ができる能力は、コンサルタントとしての信頼性を大きく高めるでしょう。
まとめ
この記事では、簿記2級の難易度、その背景にある理由、そして独学で合格を勝ち取るための具体的な戦略について詳しく解説してきました。
結論として、簿記2級は確かに難関資格ですが、その難しさの正体を理解し、正しいアプローチで臨めば、決して乗り越えられない壁ではありません。
合格への鍵は、合格率が比較的高い「ネット試験」を戦略的に選択すること、そして多くの受験者がつまずく「工業簿記」を、出題パターンが安定した得点源として早期にマスターすることにあります。
もちろん、その土台として簿記3級の知識を完璧に固め、最新の教材を用いて地道な演習を繰り返す努力が不可欠です。
簿記2級の取得には相応の学習時間が必要ですが、経理・財務から経営企画、コンサルティングまで、幅広いキャリアの扉を開く非常に価値の高い資格です。
本記事で紹介したポイントを羅針盤とし、自信を持って学習の海へ漕ぎ出し、輝かしいキャリアをその手に掴んでください。
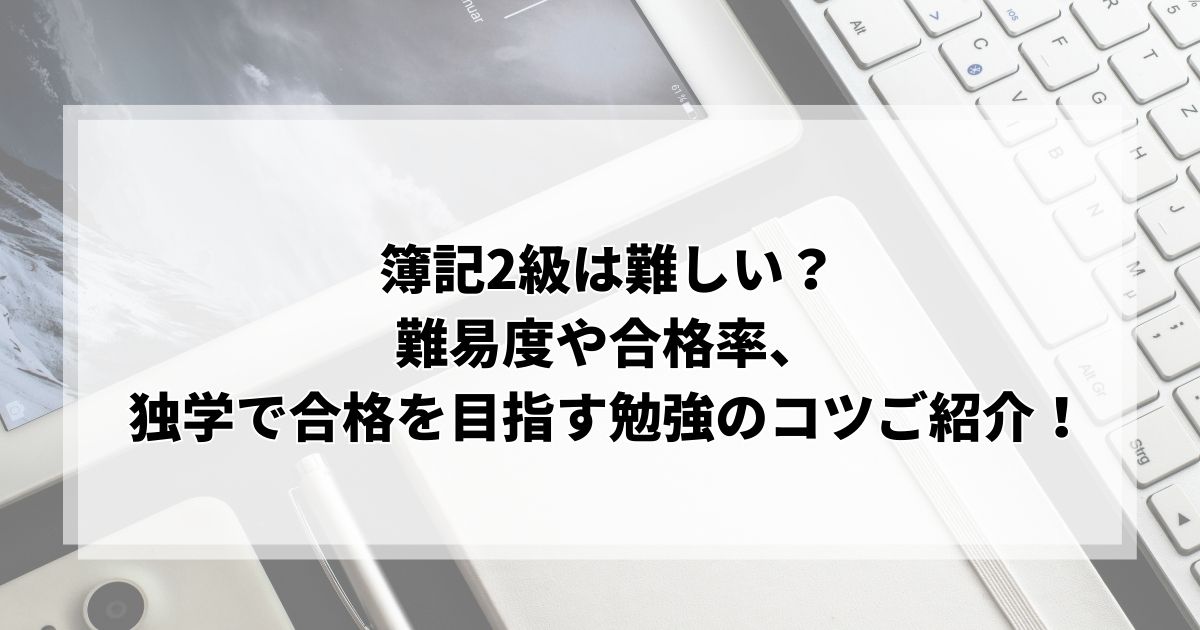

コメント